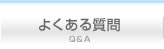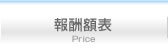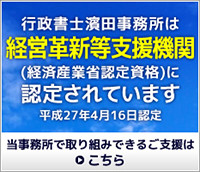NPO法人設立
1.NPO(Non Profit Organization)法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づいて所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)から認証を受けた民間の非営利組織(団体)の法人です。
株式会社や他の有限・合同・合資会社などが利益を出資者に分配(配当)するのに対し、NPO法人は非営利組織のため、社員(従業員ではなく総会で議決権を行使できる人)や寄附者に分配するのではなく、今後の事業に使用します。ただし、従業員の人件費は分配ではないので支払うことができます。
2.NPO法人設立の要件
<1> 所轄庁への認証
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、所轄庁が受理した日から2カ月間縦覧し、市民の目からも点検されます。
確認は原則、書面審査によって行われます。設立の認証後、登記することにより法人として成立します。
所轄庁は、申請が設立要件を満たすと認められるときは認証しなければならないため、法人化が公益法人に比べると容易です。
○特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、営利を目的としないこと
○社員の資格について、不当な条件をつけないこと
○役員のうち報酬を受ける役員数が、総数の1/3以下であること
○宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
○特定の公職者、政党を推薦、支持、反対することを目的しないこと
○暴力団または暴力団の構成員、もしくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下の団体でないこと
○10人以上の社員がいること
<2>役員
○理事3人以上および監事1人以上を置かなければならない
○理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定する
○役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出が必要
○役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬対象者の数等に制限が設けられている
<3>総会
○毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければならない
○社員総会の決議について、書面等による社員全員の同意の意思表示に替えることができる
<4>その他の事業
○特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、『その他の事業』を行うことができる
○その他の事業で生じた利益は、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない
○また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければならない
○利益は本業(特定非営利活動)にのみ使用する
○支出は総支出額の2分の1以下であること(NPO法の運用指針)
<5>事業報告書等
○前事業年度の事業内容報告義務
事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書、貸借対照表)、財産目録などを作成し、所轄庁に提出する。また、すべて事務所に備え置き、社員および利害関係人が閲覧できる状態にする必要がある。
○法人会計を適正に行う
法人の会計については、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければならない
<6>定款変更
定款を変更するためには総会の議決を経たうえで、一部事項に関する変更を行う場合は、所轄庁の認証が必要です。
○目的
○名称
○その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
○主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
○社員の資格の得喪に関する事項
○役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
○会議に関する事項
○その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
○解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
○定款の変更に関する事項
<7>合併、解散
○総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、別のNPO法人との合併または解散を行うことができます。
○残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、その定めがない場合は、国または地方公共団体に譲渡することができます。また、定款で定めた者に帰属しない場合及び国または地方公共団体に譲渡しない場合は、国庫に帰属することとなります。
<8>監督等
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、NPO法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また場合によっては改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことができます。また、法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。
3.NPO法人のメリットとデメリット
メリット
<1>誰でも資金なしで設立することができる
資本金が必要ないだけではなく、申請手数料、定款認証手数料(収入印紙)、登記手数料(登録免許税)も不要です。
<2>信用力が増す
民間の非営利団体の中には法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数ありますが、法人格の取得により銀行で口座を開設したり、土地の登記などを行う場合、団体の代表者個人の名義を使うことなく、団体自身の名義で行うことができるようになります。
<3>税法上で優遇されている
一般の株式会社や有限会社などの収益法人と比べると税法上で優遇されています。収入印紙の貼付は免除されています。法人住民税については所得の有無にかかわらず原則支払う必要がありますが、収益事業を行わない団体は減免の手続きで免除される場合があります。収益事業外の事業から生じた収益についても原則課税されませんので、会費と寄付金を中心に事業を運営している場合はほとんど税金がかかりません。
<4>官公庁から事業委託が受けられる
官公庁からの事業の委託は、通常は責任の所在が明確である法人に限定しているので、NPO法人化することで任意団体では受けられない事業委託を受けることが可能になります。
デメリット
<1>特定非営利活動として活動範囲が制限される
特定非営利活動促進法で定める医療・福祉・教育・子どもの健全育成などの不特定かつ多数の利益の増進に寄与する20分野に制限されています。また、所轄庁への事業報告書などの提出や、市民に対しての情報公開を行う必要があります。
<2>法人の規定に従った権利義務を負うことになる
NPO法人も法人税の課税対象となります。国が課す法人税・地方公共団体が課す法人住民税、法人事業税税法上の収益事業の利益分には税金が掛かります。
法人税については、法人税法に規定された「収益事業」から生じる所得に対して課税されることとなり、それ以外の事業から生じた収益については課税されません。
法人住民税(均等割)は所得の有無にかかわらず原則支払う必要があります。
<3>明確な会計処理が必要になる
事業報告書や収支計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿、社員名簿を毎年所轄庁に提出し、市民に閲覧されるため、透明性の高い会計を行う必要があります。また、特定非営利活動以外の事業(その他の事業)を行う場合、それに関する会計は特定非営利活動に係る会計から区別しなければなりません。
<4>立上げに手間と時間がかかる
他の法人に比べると、所轄庁の認証も必要となり、書類作成の量も多く、手間と時間がかかります。
<5>その他
○政府や民間の助成財団からの助成金は、ほとんどの場合用途が活動経費のみに制限されています。
○株式会社や有限会社などの営利法人と比べると金融機関からの融資が得にくい。
4.認定NPO法人とは
一定の基準を満たし所轄庁から認められると、『認定NPO法人』として税の優遇措置を受けることができます。
<1>認定NPO法人となるための基準
ⅰパブリックサポートテスト(PST)に適合していること
いずれか一つを各法人が選択し、申請時に報告します。広く市民からの支援を受けているかどうかを判断する基準。
【相対値基準】
総収入額のうち、寄付金収入の占める割合が1/5以上である
【絶対値基準】
「年3000円以上の寄付金」を「年平均100人以上」受ける
【条例個別指定】
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある自治体の条例により、個別指定を受けていること
ⅱ事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
ⅲ運営組織および経理が適切であること
ⅳ事業活動の内容が適正であること
ⅴ情報公開を適切に行っていること
毎事業年度1回、役員報酬規程等や事業報告書等を所轄庁に提出します。
また、書類の閲覧請求があった場合は、その事務所において閲覧できるようにしておく必要があります。
※2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合、所轄庁以外の都道府県にも提出が必要です。
ⅵ法令違反、公益に反する事実がないこと
ⅶ設立から1年を超える期間が経過していること
上記基準を満たしていても、暴力団または暴力団もしくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。
※仮認定制度…2012年4月の改正NPO法施行(1回に限りスタートアップ支援としてPSTを満たせていなくても、他要件を満たしていれば、認定扱いをしてくれる)
<2>認定の有効期間
所轄庁の認定の日から起算して5年、仮認定は3年
更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の、満了の日の半年から3か月前までの間に有効期間の更新の申請をする。
<3>認定NPO法人のメリット
ⅰ個人が認定NPO法人に寄付した場合、寄付金控除が適用される
確定申告をすることで、税金の還付を受けられます。所得控除または税額控除のいずれかを選択適用します。
ⅱ法人が認定NPO法人に寄付をした場合、損金に算入できる金額が拡大される
「特別損金算入限度額」扱いとなり、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
(資本金等の額×0.25%+所得金額×5%)×1/2
ⅲ相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合、寄付をした相続財産は相続税が非課税
ただし、仮認定NPO法人は適用外となります。
ⅳ「みなし寄付金制度」による減税措置
認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合「みなし寄付金制度」による減税措置を利用できます。
収益事業から得た利益を本来目的の非収益事業に使用した場合、この分を寄付金とみなし、一定の範囲で損金に算入
できるという制度です。結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。(仮認定NPO法人は適用外)
※2012年4月のNPO法改正でみなし寄付金の控除上限額は「所得の50%」か「200万円」のいずれか高い方に拡充
5.設立の流れ
NPO法人設立完了までの流れをご紹介します。
<1>当事務所にて打ち合わせ
面談、メール、電話等にてお客様との打ち合わせを実施します。
お勤めの方は、夜でも、土日でも、打ち合わせ可能です。
<2>NPO法人は設立登記の前に所轄庁の認証を受ける(約4カ月)
所轄庁の条例で定めるところにより、申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けます。
【添付書類】
○定款
○役員名簿
○役員の就任許諾及び誓約書の謄本
○役員の住所または居所を証する書面
○社員のうち10人以上の氏名および住所または居所を示した書面
○確認書
○設立趣旨書
○設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
○設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
○ 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
<3>書類の縦覧
所轄庁は遅延なく、以下の事項を公告し、添付書類の一部を受理した日から2カ月間公衆の縦覧に供する必要があります。
【公告事項】
○申請のあった年月日
○申請に係るNPO法人の名称、代表の氏名および主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的、提出書類に不備があるときは、誤字・脱字など軽微なものに限り、申請書を受理した日から1カ月に満たない場合補正できます。
<4>認証または不認証の決定
所轄庁は、申請を受理した日から4カ月以内に認証または不認証の決定を行い、書面により通知します。
<5>法人成立後の登記
設立承認後、申請者が主たる事務所の所在地において設立認証の通知があった日から2週間以内に設立の登記を行います。(登記に1カ月程度必要)
<6>法人成立後の届出
NPO法人は、登記により法人として成立した後、延滞なく所轄庁に届け出なければなりません。
設立の認証があった日から半年を経過しても登記をしないときは、認証を取り消されることがあります。
【法人設立後の届出書類】
○設立登記完了届書
○登記事項証明書
○設立時の財産目録
【設立後の定款変更手続き】
○所轄庁への申請書類作成:3~7日
○所轄庁での縦覧期間:2カ月
○所轄庁での審査期間:1カ月半から2カ月
○法務局での設立登記書類の処理期間:約7日
NPO法人の設立をお考えなら、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所では仙台市内をはじめ、宮城県内の法人設立を代行しております。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。