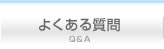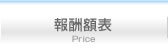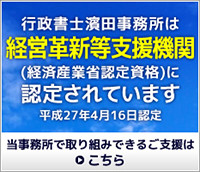有料老人ホーム設置
1.有料老人ホーム
老人福祉法第29条に規定されている、65歳以上の高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて生活サービスを提供することを目的とした施設です。ただし、老人福祉法上の老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)に分類されるもの、認知症高齢者グループホームは除きます。
設置には都道府県知事へ、事前に届出が必要です。各都道府県で定めた『設置指導指針』『設置指導要綱』に基づいて事前協議等の手続きを進める必要があります。
仙台市内に有料老人ホームを設置する場合は、宮城県知事からの事務移譲により、仙台市長に届出が必要です。仙台市で定めた『設置指導指針』『設置指導要綱』で手続きを進めます。
※当事務所では、合同会社による住宅型有料老人ホームの開設や通所介護(デイサービス)、居宅介護支援(ケアマネ)を併設した住宅型有料老人ホームなどの立ち上げを計画段階から開所まで、ご支援した実績があります。
住宅型有料老人ホームの届出書類一式を作成するだけではなく、土地を購入して有料老人ホームを建築する際の資金調達、銀行借入のご支援、助成金のコンサル(地域雇用開発奨励金など)総合的にお手伝いさせていただくことも可能です。
住宅型の有料老人ホームを設置するにあたっては、まずは候補予定地の用途地域の調査から入り、施設基準を満たしているかの図面の確認、行政への事前協議を行っていきます。ちょっとわかりにくいですが、詳細は下記のとおりです。事前協議が終了後は、工事の進捗具合に合わせて、届出すべきを届出していきます。
仙台市や宮城県の保険事務所だけの届出だけではなく、消防法上の防火管理責任者や消防計画などの届出(消防署への届出書類)をみなさん忘れがちになりますので、ご注意してください。
老人ホームの類型はさまざまあり、比較的開設しやすいのが住宅型老人ホームになります。介護付老人ホーム、グループホームなどは、各市役所の介護計画により計画されていますので、行政の意向確認が必要です(宮城県内には介護付き有料老人ホームはほとんどないと聞いています)。また、地域密着型や特養老人ホームなど、社会福祉法人でなければ運営できない老人ホームがありますので、ご注意してください。
2.有料老人ホームの類型(参考)
<1>介護付き有料老人ホーム
○一般型特定施設入居者生活介護
介護や食事等のサービスが付いた有料老人ホームで、介護保険で定められた基準を満たし、特定施設入居者生活介護に指定された施設です。運営事業者が介護サービスも提供します。
○外部サービス利用型特定施設入居生活介護
介護や食事等のサービスが付いた有料老人ホームですが、介護サービスは委託先の介護サービス業者が提供します(老人ホーム経営事業者と介護事業者が別となります)
○地域密着型特定施設入居者生活介護
介護や食事等のサービスが付き、指定を受けた入居人数30人未満の有料老人ホームです。
原則として届出を行った市町村の人が利用します。また、要支援1・2の人は利用できません。
○介護予防特定施設入居者生活介護
要支援1・2の人のみ利用できます。
<2>住宅型有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームのように施設が提供する一律の介護サービスではなく、介護の種類やサービス提供先は入居者の選択により訪問介護など外部の在宅介護サービスを利用します。
<3>健康型有料老人ホーム
自立した高齢者を対象にした有料老人ホームで、食事等のサービスを提供します。
介護サービスは提供できないので、介護が必要となった場合は契約を解除して退去する必要があります。
3.有料老人ホーム設置要件(宮城県の場合)
有料老人ホームの設置要件で主なものは次の通りです。
仙台市内に有料老人ホームを設置する場合は、宮城県知事からの事務移譲により仙台市長に届出が必要です。仙台市の『有料老人ホーム設置運営指導指針』『有料老人ホーム設置指導要綱』に基づき事前協議等の手続きを進める必要があります。
<1>設置主体
老人福祉施設と異なり、地方公共団体や社会福祉法人に限定されません。そのため、株式会社等の法人が設置することも可能です。公益法人の場合は主務官庁の承認が必要です。
○事業を確実に遂行できる経営基盤が整っており、社会的信用の得られる経営主体であること
○個人経営でないこと。少数の個人株主等による独断専行的な経営体制でないこと
○役員の中に有料老人ホームの運営について知識・経験のある者がいること
○他の事業を営んでいる場合、その財務内容が適正であること
<2>立地条件
入居した高齢者が長期間にわたり生活する場であることから、健康で安全な生活を維持できるよう、交通や医療機関との連携、環境に配慮された立地である必要があります。
○住宅地から遠距離でなく、入居者が外出する際に不便な地域でない
○その土地および建物について有料老人ホーム事業以外の目的による抵当権など有料老人ホームとしての利用を制限する恐れのある権利が存在しないことが、登記簿謄本や現地調査等により確認できること
○街化調整区域に設置を予定している場合、宮城県開発審査会提案基準に該当し、開発許可及び建築許可の見込みがあること
○借地・借家により設置する場合は長期安定契約の諸条件を満たしていること
<3>構造設備
○建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模および構造設備を有すること
○建物は、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物とし、避難設備、消火設備、警報設備その他地震、災害、ガス漏れ等の防止や事故災害に対応するための設備を十分に設けること
(知事が有識者の意見を聴き、入居者の安全が確保されていると認めたときはこの限りではない)
○建物の設計にあたっては、入居者の身体機能が低下した場合や障害が生じた場合にも対応できるように配慮すること。
○提供するサービス内容に応じ、次の設備を設けること
ⅰ一般居室または介護居室、一時介護室
個室とし、入居者1人あたりの床面積は13平方メートル以上とする。各個室は界壁により区分されたものとする。
ⅱ食堂
ⅲ浴室
要介護者が使用する浴室は、身体の不自由なものが使用するのに適したものとすること
ⅳトイレ
要介護者が使用するトイレは、居室内または居室のある階ごとに居室に近接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに身体の不自由なものが使用するのに適したものとすること
ⅴ洗面設備
ⅵ医務室または健康管理室
医療法施行規則に規定する診療所の構造設備の基準に適合したもの
ⅶ談話室または応接室
ⅷ洗濯室、汚物処理室、看護・介護職員室、機能訓練室、健康・生きがい施設
<4>職員の配置
ⅰ職員の配置
職員の配置については、入居者の数および提供するサービス内容に応じ、その呼称に関わらず次の職員を配置します
施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員(看護師または准看護師)、機能訓練指導員、栄養士、調理員
ⅱ入居者の実態に即し、夜間の介護および緊急時に対応できる数の職員を配置します
ⅲ介護サービスを提供する有料老人ホームの場合
○要介護者を直接処遇する職員の数は、要介護者等を3で除した数以上とする
(直接処遇職員…生活相談員、介護職員、看護師または准看護師)
○看護師は、入居者の健康管理に必要な数を配置すること。看護師の確保が困難な場合には准看護師を充てることが出来ます
○施設長等介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者介護についての知識、経験を有する者であること
ⅳ職員の研修
職員に対しては、採用時および採用後において定期的に研修を実施すること。特に直接処遇職員については高齢者の心身の特性、実施するサービスの在り方および内容、介護に関する知識及び技術ならびに作業手順等についての研修を行う
ⅴ職員の衛生管理
職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見および健康状態の把握のために、定期的に健康診断を行うとともに、就業中の衛生管理面について十分な点検を行うこと
<5>施設の運営・管理
ⅰ管理規程等の制定
入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準並びに医療を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けます。
ⅱ名簿等の整備
入居者およびその身元引受人等の氏名および連絡先を明らかにした名簿、設備、職員、会計に関する帳簿及び入居者の状況費用の受領の記録、提供したサービスの内容、苦情に関する記録等の事項については、帳簿を作成し、2年間保存します。
ⅲ緊急時の対応
事故・災害および急病・負傷に対して迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計画を立てるとともに、避難計画等必要な訓練を定期的に行う。また、消防法等に基づいた防災体制を整備します。
ⅳ医療機関との連携
提携(協力)医療機関を定め、その診療科目等について入居者および身元引受人に周知しておきます。また、協力歯科医療機関を定めるよう努めます。
ⅴ運営懇談会の設置
4.設置の手続き(宮城県の場合)
<1>設置にあたっての事前相談
都市計画法、建築基準法の確認申請前に設置計画事前協議書により設置設計の詳細等について知事と協議します。
<2>設置にあたっての事前協議
事前協議書には、設置予定地の市町村長の有料老人ホーム設置同意書を正副各1部添付します。
知事は事前協議書の内容を審査、指針・規程に適合していると認められる場合、有料老人ホーム設置計画事前協議済書を交付します。事前協議済書を受領した後に開発許可、建築許可または確認申請を行います。
(市街化調整区域における事前協議)
知事は、市街化調整区域において有料老人ホームの設置を予定している者に対し、事前協議済書を交付する場合、開発審査会提案基準(優良な有料老人ホーム)に該当するかどうか確認します。
<3>設置届の提出
開発許可、建築許可または建築確認を受けたら速やかに設置の届出を行います。事前協議書、社団法人全国有料老人ホーム協会の入会資格審査委員会審査結果の通知の写しを添付します。
知事は、設置届を受理したときは有料老人ホーム設置届受理書を設置予定者に交付します。
設置予定者は、設置届受理書の交付を受ける前に入居者の募集を行ってはいけません。
<4>施設設備工事着手
有料老人ホーム設置に係る工事の着工は、相当数の入居者が見込まれていない場合においては、入居一時金の返済債務について銀行保証が付されたあとに行わなければなりません。工事に着工しようとするときは、あらかじめ入居見込者名簿および建設工事工程表を添付した建設工事着工届書を知事に提出します。
<5>特定施設入居者生活介護指定申請(介護付き有料老人ホームの場合のみ)
介護付き有料老人ホームの場合は特定施設入居者生活介護の指定を受けます。事業所の所在する都道府県に事業開始予定日前々月末までに申請します。
※介護保険法に関わる指定申請については提携する社会保険労務士と連携して行います。
<6>施設運営開始
有料老人ホームの運営を開始したときは、事業開始届書を知事に提出しなりません。事業開始届出書には、重要事項説明書、および有料老人ホーム介護サービス等の一覧表並びに建物引き渡し関係書類の写しを添付します。
※事業変更届…届出の内容に変更が生じたときは、速やかに事業変更届を知事に提出します。
◆設置後は、定期報告として毎年7月1日現在の有料老人ホーム重要事項説明書および有料老人ホーム介護サービス等の一覧表を作成し、同月末日までに知事に報告する必要があります。
また、役員または施設長に変更があった場合、入居契約書または管理規程を変更する場合、利用料を改定した場合、重大な事故が発生した場合は随時報告します。
有料老人ホームの開所をお考えなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。