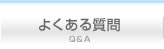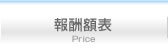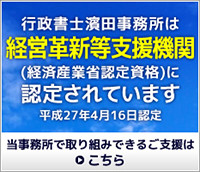通所介護事業(デイサービス)
1.通所介護とは
日常生活を送るうえで必要な入浴・排泄・食事等の日常生活の支援や、生活機能向上のためのグループ活動等、利用者が日帰りで高齢者デイサービスセンター等を訪れて受けるサービスです。
自宅や有料老人ホームなどの「居宅」「居室」で生活を送る「要支援」「要介護」認定された人が利用できます。
2.通所介護事業指定
通所介護(デイサービス)事業を行うためには、都道府県または市区町村に申請を行った指定介護事業者でなければなりません。
指定介護事業者となるためには、様々な要件を満たす必要があります。
<1>人員基準
ⅰ生活相談員(1人以上)
通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者が1人以上必要です。社会福祉士・社会福祉主事・精神保健福祉士の資格が必要です。都道府県によっては介護福祉士(実務経験年数)でも可能な場合があります。
ⅱ看護職員(1人以上)
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はありませんが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者が1名以上必要です。看護師・准看護師の資格が必要です。利用定員が10人以下の場合は、看護職員または介護職員が1人以上必要となります。(利用定員により、常勤、非常勤換算あります)
ⅲ介護職員(15人までは1人以上、15人を超えたら超えた利用者数÷5に1を加えた数以上を配置)
通所介護の提供を行う時間数に応じて、利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要になります。利用者数が15人を超える場合は、5人おきに専従の介護職員をプラスしていきます。1人の端数でも増員が必要です。資格要件は特にありません。
ⅳ機能訓練指導員(1人以上)
看護師・准看護師・理学療法士・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・作業療法士・言語聴覚士のいずれかの資格保持者が1人以上必要です。
ⅴ管理者(常勤1人以上)
専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要です。常勤の生活相談員・機能訓練相談員・看護職員・介護職員との兼用は可能です。特に資格要件はありません。
※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤(利用定員10人以下の場合は、生活相談員・看護職員または介護職員のうち1人以上)とします。
<2>設備基準
ⅰ食堂および機能訓練室
それぞれ必要な広さを有し、その合計面積は3㎡×利用定員の面積以上必要です。また、食堂および機能訓練室は、食事提供・機能訓練の実施に支障ない広さを確保できる場合は、同一の場所とすることができます。
ⅱ相談室
遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないように配慮されている必要があります。
ⅲ静養室
利用定員に対して適当な広さを確保します。小規模でもベッドを2台設置するよう指導される場合もあります。機能訓練室から見通しのきく場所に設置します。
ⅳ事務室
従業員・設備・備品を配置できるスペースを設けます。
ⅴトイレ
介助に適した構造、設備とします。
ⅵ厨房
食事を提供する場合に設置します。
ⅶ浴室・脱衣室
手すりを設置し、利用者の安全に配慮します。
※消化設備その他の非常災害に際して必要な設備、ならびに通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなりません。
<3>運営基準
ⅰ法定代理受領サービス外に係る費用について
利用者の選択によって法定代理受領サービスを超えたサービスに係る費用(通常サービス地域外の利用者の送迎費・超過時間・食材費、おむつ代、日常生活に必須な物品の費用)については、利用者同意のうえで受領します。また、法定代理受領サービス外の介護サービスについて、利用者から支払を受ける額が基準額と不合理な差があってはなりません。
ⅱ通所介護計画書の作成について
管理者は、利用者の希望および置かれている環境を踏まえ、目標を達成するための具体的なサービス等を記載した通所介護計画書を作成し、利用者・家族に対して内容を説明し、同意を得なければなりません。
ⅲ従業員の勤務体制の明確化
利用者に適切なサービスを提供できるよう、従業員の勤務体制を定めておく必要があります。
ⅳ利用定員の順守
災害時等やむを得ない事情がある場合以外、利用定員を超えて介護サービスの提供を行ってはなりません。
ⅴ非常災害時の対応について
非常災害に対する具体的な計画を立て、定期的に従業員に周知するとともに、必要な訓練を行う必要があります。
ⅵ衛生管理
利用者の使用する施設・食器・その他の設備・飲用水について衛生的な管理と必要な措置を講じなければなりません。
ⅶ記録の保管について
従業員・設備・備品・会計に関する諸記録を整備しなければなりません。
通所計画書、具体的なサービス内容等の記録、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況及び処置の記録は、完結の日から2年間保存する必要があります。
3.通所介護事業者の指定申請まで
通所介護事業者の指定を申請するまでの流れをご紹介します。
<1>サービス内容の決定
予算、施設の立地、通常サービス地域、サービスの内容等を決定します。
<2>施設の物件確保
介護事業者の施設基準に配慮し、物件の選定・設計を行います。
<3>事業計画書の作成
事業内容、資金計画、収支計画を立てます。
<4>法人の設立
通所介護指定の許可を取得するためには、法人格が必要です。
<5>指定機関との事前協議
施設・設備について、指定機関と工事着工の前に事前協議します。
<6>人員の募集
人員基準で決められたスタッフを確保します。
<7>通所介護事業者の指定申請
工事完了後、必要書類を添えて指定機関(都道府県または市町村)に申請します。
※介護保険法に関わる指定申請については提携する社会保険労務士と連携して行います。
また、指定介護事業者の指定申請の他にも、事業計画書の作成や法人の設立等についてもサポートしております。
介護事業の開業をお考えなら、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。