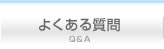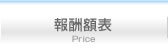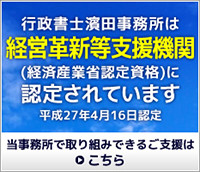訪問介護指定申請
1.訪問介護指定
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように食事・排泄・入浴等の身体介護や、食事・排泄・入浴等の生活援助を行います。
訪問介護では、利用者の家族のための家事等、直接利用者の援助に該当しないサービスや、ペットの世話等、日常生活の援助の範囲を超えるサービスは対象外となります。
2.訪問介護事業の開業要件
訪問介護事業の開業には、都道府県から指定介護事業者指定の指定(許可)が必要です。
<1>法人格を有する
新たに株式会社・合同会社・NPO法人・医療法人等の法人を設立するか、既にある法人の定款の事業目的に訪問介護支援事業を追加します。
<2>人員基準
ⅰ訪問介護員
常勤換算方法で2.5人以上(職員の支援体制等を考慮した最小限の員数。各地域におけるサービス利用の状況や利用者数および業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保します)の訪問介護員の確保が必要です。
※登録訪問介護員等(勤務日および勤務時間が不定期な訪問介護員等)についての勤務延時間数の算定
【登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある場合】
1人当たりの勤務時間数=当該事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び移動時間)
【登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない場合】
当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入する出張所等があるときは、訪問介護員等の勤務延時間数に、出張所等に置ける勤務延時間数も含めます。
ⅱサービス提供責任者
利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません(最小限必要な員数)。管理者がサービス提供責任者を兼務できます。
利用者の数は、前3カ月の平均値を使用します。新たに事業を開始、または再開した場合は適切な方法により利用者数を推定します。通院等乗降解除に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1人として計算します。
サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数の2分の1以上に達している者でなければなりません。
【サービス提供責任者の任用要件】
3年以上介護等の業務に従事した者(原則としてボランティアとして介護等を経験した期間は含まれない)であって、2級課程を修了した者。尚、指定訪問介護事業者は、サービス提供責任者に介護福祉士の資格を取得させるよう努めます。
訪問介護員等のうち、介護福祉士その他知事が定める者であって、原則として常勤のものから専任するものとされていましたが、その具体的取扱は次のとおりです。
○専ら指定訪問介護の職務に従事する者
○同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または指定夜間対応訪問介護事業所の職務に従事することができること。この場合、同時並行的に行われることが差支えないと考えられるものであることから当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。
ⅲ管理者
指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとします。当該事業所の管理業務に支障がない場合、他の職務を兼ねることができます。管理者は訪問介護員等でなくても可能です。
<3>設備基準
事務室・相談室・会議室等、事業に対応できるスペースがある事務所が必要です。また、相談室はプライバシーに配慮した構造とします。指定訪問介護の提供に必要な設備および備品等を備えます。
<4>運営基準
運営に関する基準は、省令で定められています。
○内容及び説明および同意
指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、サービス提供に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければなりません。
利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましい。
○提供拒否の禁止
正当な理由ではなく、要介護度や所得の多寡等を理由としたサービスの提供を拒否することを禁止します。
○サービス提供困難時の対応
正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、適当なほかの指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければなりません。
○受給資格等の確認
指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られているものであることを踏まえ、サービス提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって資格・認定の有無や有効期間を確かめなければなりません。
また、利用者の被保険者証に留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮してサービスを提供するように努めなければなりません
○身分を証する書類の携帯
利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携帯させ、利用者から求められた場合提示すべき旨を指導しなければなりません。
○サービス提供の記録
利用者およびサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサービス利用状況を把握できるよう、指定訪問介護事業者は、サービス提供日、内容、保険給付の額、その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画の書面またはサービス利用表等に記載しなければなりません。
なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は5年間保存する必要があります。
○利用料等の受領
法定代理受領サービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の1割の支払を受けなければなりません。
また、利用者間の公平および利用者保護の観点から、法定代理サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはなりません。介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されます。
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合の交通費の支払を利用者の同意を得て受けることができ、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認められません。
○訪問介護計画の作成
訪問介護計画は居宅サービス計画に沿って作成されなければなりません。
サービス提供責任者は、利用者の状況を把握・分析し、サービスの提供によって解決するべき問題状況を明らかにし、これに基づき援助の方向性や目標・担当訪問介護員・提供サービス・日程等を明らかにした訪問介護計画を作成しなければなりません。
また、他の訪問介護員等の行うサービスが計画に沿って実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要管理を行います。
訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて作成されなければならないものであり、内容について利用者に説明を行い同意を得ることを義務付けることにより、利用者の意向の反映の機会を保証するものとします。
訪問介護計画を作成した際は、遅延なく利用者に交付し、5年間保存する必要があります。
○緊急時等の対応
指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は運用規定に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに主治医へ連絡する等の必要な措置を講じなければならなりません。
○衛生管理等
訪問介護員等の清潔の保持および健康状態の管理ならびに指定訪問介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めること。特に訪問介護員等が感染源となることを予防し、感染の危険から守るため、使い捨て手袋等感染を予防するための備品を備える等対策を講じる必要があります。
○秘密保持義務
介護支援専門員その他の従業員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはなりません。また、過去に従業者であった者が秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければなりません。
○居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
指定訪問介護事業者は、巨額介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなりません。
○苦情処理
相談窓口、苦情処理の体制および手順等当該事業所における苦情を処理するための措置の概要について明らかにし、利用者等にサービスの内容を説明する文書に併せて記載するとともに、事業所に掲示します。
利用者等からの苦情に対し、受付日、内容等を記録を義務付けし、5年間保存しなければなりません。
また、国民健康保険団体連合会だけでなく市町村についても苦情に関する調査や指導、助言を行えるものとします。
○地域との連携
介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村と密接な連携に努めなければなりません。
○事故発生時の対応
指定訪問介護事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じ、事故の状況およびその際に採った処置について記録し、5年間保存しなければなりません。
また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う必要があります。
○会計の区分
指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。
3.訪問介護事業書の指定申請に必要な書類
【申請に必要な書類】
○指定申請書
○(介護予防)訪問介護事業所の指定に係る記載事項
○申請者の定款、寄付行為等の写しおよび登記事項証明書または条例等
申請者が法人であることを確認するための書類
(原本証明した定款等の写しと登記事項証明書(原本)を添付)
○勤務表
○従業者の資格証の写し(訪問介護員等であることの証明)
○従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
○管理者の経歴書
○事業所の平面図
○運営規程
○苦情を処理するための措置概要
○資産の状況
損害保険証書の写し、資産の目録、直近の決算書または当該年度の事業計画書・収支予算書
○誓約書
○管理者および役員名簿
※当事務所では,介護保険法に関わる指定申請については提携する社会保険労務士と連携して行います。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。