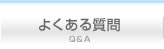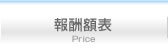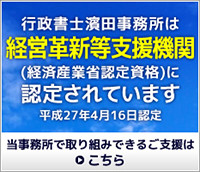特養老人ホーム
1.特養老人ホームとは
特養老人ホーム(特別養護老人ホーム)とは、要介護1から5の認定を受けた65歳以上の方を対象とし、身体上または精神上著しい障害により、常に介護が必要な状態で、居宅において介護が困難な場合に入所する施設です。要介護者に対して介護保険サービスを行う施設が特別養護老人ホームです。入所は『入所検討委員会』が決定し、入所条件は市区町村によって異なります。
設置・運営は都道府県、市町村または社会福祉法人に限定されています。設置には所轄庁に事前に届出が必要です。各所轄庁で定めた『設置指導指針』『設置指導要綱』に基づいて事前協議等の手続きを進める必要があります。
仙台市内に有料老人ホームを設置する場合は、宮城県知事からの事務移譲により、仙台市長に届出が必要です。仙台市で定めた『設置指導指針』『設置指導要綱』で手続きを進めます。
※特養老人ホームは、社会福祉法人での運営しか認められておらず、また、特養老人ホームは行政の介護計画(プラン)によりますので、必ず開所できる訳ではありませんので、ご留意ください。
2.特養老人ホームの類型
<1>特別養護老人ホーム(従来型)
多床室(定員4人以下)と一部個室の従来からある特別養護老人ホームです。
<2>ユニット型特別養護老人ホーム
居宅に近い居住環境で、居宅での生活に近い日常生活の中でケアをすることを目的とした特別養老老人ホームです。ユニットごとにケアを行うことが特徴で、居室は個室タイプの定員1人が原則で、ユニットごとに共同生活室が設置されます。
<3>地域密着型特別養護老人ホーム
小規模(30人未満)でより地域に密着した居住環境のもとでケアを行うことに特徴があります。地域密着型特別養護老人ホームには様々な形態があります。
○単独の小規模の特別養護老人ホーム
○本体施設のあるサテライト型居住施設
○指定居宅サービスや指定地域密着型サービス事業所と併設された小規模の特別養老老人ホーム
サテライト型居住施設とは、本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体設備とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいいます。
3.特養老人ホーム設置要件
特養老人ホームの設置要件で主なものは次の通りです。
<1>設置主体
地方公共団体または社会福祉法人に限定されています。
<2>立地条件
入居した高齢者が長期間にわたり生活する場であることから、健康で安全な生活を維持できるよう、交通や医療機関との連携、環境に配慮された立地である必要があります。また、社会福祉事業を行う直接必要なすべての物件について所有権を有すること、または国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けている(施設の種類によっては緩和措置があります)必要があります。都市計画法、建築基準法、宅地開発指導要綱等で規制された土地、建物でないか確認しておきます。
<3>構造設備
特別養護老人ホームでは、次の設備を設けます。
居室、静養室、浴室、トイレ、洗面設備、医務室、調理室、洗濯室、食堂および機能訓練室
<4>職員の配置
職員の配置については、入居者の数等に応じ、その次の職員を配置します。
施設長、機能訓練指導員、生活相談員、看護職員(看護師または准看護師)または介護職員、栄養士、調理員、事務員、その他職員、ケアマネージャ(介護支援専門員)
4.施設の運営・管理
<1>入所定員
入所定員は、特養老人ホームの専用の居室のベッド数(和室利用の場合は居室の利用人員数)と同数とする(従来型の場合)。
<2>入所者の処遇の内容および費用の額
日常生活を送る上での1日当たりの日課やレクリエーションおよび年間行事等を含めた処遇の内容を指すものであること。費用の額については介護保険等の費用の内容の他、日常生活等の上で入所者から支払を受ける費用の額を規程するものであること。
<3>施設の利用に当たっての留意事項
入所者がホームを利用する際の留意すべき事項(生活上のルール、設備の利用上の留意事項等)
<4>非常災害対策
○非常災害に際して必要な措置に関する計画の策定、消防機関等への通報および連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等その対策の万全を期さなければならないこと。消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を確実に設置しなければならない。
○非常災害時は、ライフラインが長時間途絶する事態が想定されることから、非常用食料、飲料水、日用品その他非常災害時に必要となるものの備蓄や、自家発電装置の整備に努める。
<5>その他施設の運営に関する重要事項
入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ましい。
<6>記録の整備
日々の運営や財産、入所者の処遇に関することを正確に記録し、常にホームの実情を把握するため、少なくとも次に掲げる記録を備える必要があります。
ⅰ運営に関する記録
事業日誌・沿革に関する記録・職員の勤務状況、給与に関する記録・条例、定款および施設運営に必要な諸規程・重要な会議に関する記録・事業計画及び事業実施状況表・関係官署に対する報告書等の文書綴
ⅱ入所者に関する記録
入所者名簿・入所者台帳・入所者の処遇に関する計画・処遇日記・献立その他食事に関する計画・入所者の健康管理に関する記録・入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に行った身体的拘束等の記録・苦情の内容等の記録・事故が発生した場合の記録
ⅲ会計経理に関する記録
収支予算および収支決算に関する書類・金銭の出納に関する記録・債権債務に関する記録・物品受払に関する記録・収入支出に関する記録・資産に関する記録・証拠書類綴
ⅳ経理の原則
特別養護老人ホームの運営に伴う収入および支出は、経営主体である地方公共団体または社会福祉法人の予算に必ず計上し、収支の状況を明らかにする必要があります。
5.設置の手続き
<1>社会福祉法人設立
ⅰ役員
○理事(6名以上)
理事には社会福祉事業について学識経験を有する者または地域の福祉関係者を加えなければなりません。また、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上の施設長等が理事として参加します。
○監事(2名以上)
当該法人の理事、評議員および職員またはこれに類する他の職務を兼務できません。監事のうち1人は財務諸表等を監査しうる者でなければなりません。
また1人は社会福祉事業について学識経験を有する者または地域の福祉関係であること。監事は他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならない。当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者であってはならない。
○評議員
定数および現員は理事の2倍を超えてはならない。各評議員と親族等の得すの関係にある者の数が、限度数を超えてはならない。当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関係する業務を行う者が3分の1を超えてはならない。評議員には地域の代表者が参加していること。また、利用者の家族の代表が加わることが望ましい。
ⅱ法人の資産等
○社会福祉法人は、社会福祉事業を行う直接必要な全ての物件について所有権を有すること、または国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること(施設の種類によっては緩和措置があります)
○運用財産として当該法人の年間事業費の12分の1以上(特別養護老人ホームの介護保険法上の事業の場合12分の2以上)に相当する現金、普通預金、または当座預金等を有していること。宮城県においては、上記に加え、開設準備に必要な経費を有していることを要します。
○基本財産または運用財産を寄附金で賄う場合は書面による贈与契約が締結されていること。
○社会福祉法人が解散する場合の残余財産については合併及び破産の場合を除き、定款の定めるところによりその帰属すべき者に 帰属するが、社会福祉法人その他社会福祉上を行う者のなかから選定されなければならない。
○社会福祉法人設立前に法人設立のために発生した事務経費等について、法人設立後に法人から支払えないので、設置者等が支払うこととなります。
<2>社会福祉法人設立にあたっての事前協議
設立時は、まず事前協議を行い、設立する法人概要を所轄庁に説明する必要があります。社会福祉施設を建設するために、国庫補助金または民間補助金の申請のための事前協議等を行いますが、これらの事前協議等と並行して法人の適否について判断していくためのものです。
【必要書類】(宮城県知事が所轄庁の場合:法人設立予定年の前年11月末までに提出)
○社会福祉法人新設調書
○法人設立趣意書または建設趣意書
○役員および評議員就任予定者の履歴書
○設立に係る法人の資産に関する書類(寄附確約書の写し、残高証明書)
○図面(土地位置図、施設平面図)
○土地の権原に係る書類(寄附確約書・売買予約書・貸与確約書の写し・不動産登記簿事項証明書)
○事業開始年度及び次年度の収支予算書
○融資証明書の写し(民間金融機関の場合)
相談の経緯について説明した書(独立行政法人福祉医療機構からの融資の場合)
<3>社会福祉法人設立許可申請
設立許可申請(本申請)は、施設建設のための補助金内示および民間補助金の内定通知があった時期に行います。
【必要書類】
○設立許可申請書
○定款
○添付書類目録
○設立当初の財産目録
○財産が法人に帰属することを証する書類(贈与契約書、確約書、補助予定通知書、身分証明書、印鑑登録証明書、残高証明書等)
○法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類(地方公共団体の無償貸与確約書、不動産登記簿謄本、土地貸借契約書等)
○設立当初の会計年度および次会計年度の事業計画書および収支予算書
○設立者の履歴書等(履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書等)
○設立代表者の権原を証する書類(設立発起人会議事録、委任状等)
○役員就任予定者履歴書等(履歴書、選定理由書、就任承諾書、身分証明書、印鑑登録証明書等)
○施設建設関係書類(施設建設計画書、建設図面、見積書、補助金予定通知書、建設自己資金に係る贈与契約書、貸付決定通知書、償還契約書、償還金財源に係る契約書、基本財産編入契約書等)
○施設庁就任承諾書(就任承諾書、履歴書、資格を証する書類)
○諸規程(就業規則、給与規程、経理規程)
<4>特別養護老人ホーム届出(宮城県長寿境政策課:仙台市役所)
【必要書類】新規の場合(添付資料は設立する特別養護老人ホームの種類や、設置場所等により異なります)
○老人ホーム設置認可申請書
○(施設開設後)老人ホーム事業開始届
市町村立、独立行政法人立の施設の設置はあらかじめ老人ホーム設置届の届出が必要です。
※当事務所は、介護保険法に関わる指定申請については提携する社会保険労務士と連携して行います。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。