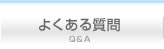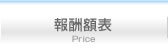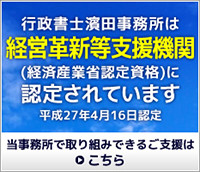著作権登録
1.著作権とは
職務多忙につき、著作権関係の仕事は、しばらくお休みします。
近年、ニュースなどで著作権侵害や知的財産権などの問題が報じられることも多くなり、著作権について考える機会も増えてきたのではないでしょうか。
著作権という言葉から、著作物を創作した人の権利であることは想像できますが、詳しいことまでわからない方が大半ではないかと思います。
著作権法は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権の一つです。
著作権は、著作物(小説、マニュアル、ホームページ、楽曲、歌詞、絵画、漫画、イラスト、写真、プログラムなど)を創作した時点で自動的に発生します(このことを難しい法律用語で「無方式主義」と言います)が、著作権の事実関係の公示や著作物を譲渡した場合における取引の安全性を確保するなどのために「登録制度」があります。
プログラム著作物は(財)ソフトウェア情報センター、それ以外の著作物は文化庁の著作権課で登録を行っています。
尚、民間会社で著作権登録を実施している会社もあるようですが、著作権法上の効力はありませんので、ご注意ください。
<1>第一発行・公表年月日等の登録
実名又は無名・変名(ペンネーム)で公表された著作物の発行者が、著作物を最初に発行した年月日もしくは最初に公表した年月日を登録することができます。 登録日に当該著作物が第一発行または第一公表されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。
また、先にどちらが創作したかが争点となるような場合においては、登録を受けておくと訴訟などで有利になる場合があります。(争いや訴訟に発展すると創作の過程が分かる資料やメモを提出する場合がありますので、捨てずに取っておきましょう)
<2>創作年月日の登録(ソフトウェアなどのプログラムのみ)
プログラムの著作者は当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。登録日に当該プログラムが創作されたと推定され、保護期間算定の起算点となります。ただし、創作後6ヶ月を経過したものは登録できない場合があります。
また、先にどちらが創作したかが争いになるような場合においては、登録を受けておくと訴訟などで有利になる場合があります。(争いや訴訟に発展すると創作の過程が分かる資料やメモを提出する場合がありますので、捨てずに取っておきましょう)
<3>実名の登録
無名または変名(ペンネームなど)で公表された著作物について、その著作者は実名(本名で)の登録を受けることができます。
無名または変名で公表された著作物の保護期間は公表後50年間ですが、実名の登録をすると著作権の保護期間が実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となりますので、保護期間が延長されます。
<4>著作権・著作隣接権の移転等の登録
著作権の譲渡・移転や著作隣接権の譲渡登録や質権の設定の登録を受けることができます。
著作権が著作物を創造した人に与えられる権利に対し、著作隣接権は著作物を伝達した人に与えられる権利で、実演者、レコード(音などを記録したもの)製作者、放送事業者、有線放送事業者が該当します。
著作権などの移転や譲渡をすることによって生ずる権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することができません。
著作権の二重譲渡があった場合、先に登録したものが権利を出張できます。この場合においては、たとえば著作権譲渡契約書なども作成し、契約をしてください。
<5>出版権の設定等の登録
登録権利者・登録義務者が出版権の設定の登録、出版権の移転の登録、出版権を目的とする質権の設定等の登録をすることができます。
出版権は登録した場合においてのみ、第三者へ対抗することができます。
2.著作物とは
著作権法で、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(法2条)と定義されています。
日本の国内において、著作物となるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
<1>思想又は感情の表現である
人間の思想や感情を伴わない単なる事実やデータは著作物ではありません。
<2>創作性がある
創作が加わっていないありふれた表現には創作性がないとされます。
<3>表現したものである
なんらかの形で表現したものでなければなりません。アイデアは表現ではないので、著作権法では保護されません。
※アイディアを保護する法制としては,特許法,実用新案法などがあります。
<4>文芸、学術又は音楽の範囲である
大量に生産する工業製品は著作権では保護されません。
3.著作物の種類
著作物の種類については、著作権法10条で例示されています。
<1>言語の著作物
小説、脚本、作文、詩、俳句、レポート、論文、講演など
<2>音楽の著作物
楽曲や楽曲を伴う歌詞など
<3>舞踊、無言劇の著作物
バレエ、ダンス、パントマイムなどの舞踏や振り付け
<4>美術の著作物
絵画、版画、彫刻、漫画、書道、茶碗や壷、刀剣などの美術工芸品等
<5>建築の著作物
建物、庭園、橋など芸術的な建築物
<6>図形の著作物
地図、設計図、立体模型など
<7>映画の著作物
劇場用の映画、アニメ、ゲームソフトの映像、ビデオなどの録画されている動画
<8>写真の著作物
写真、グラビアなど
<9>プログラムの著作物
コンピュータのプログラム
※コンピュータに対する指令の組み合わせであって、1+1=2のような誰が作っても
結果が同じのような単純なプログラムは著作物ではありません。
★二次的著作物
小説を映像化したもの、英語の小説を日本語に翻訳したもの、既存の楽曲を編曲したものなどは「二次的著作物」と言われます。
原作に新たな創作を加えたものについては、別の著作物として、保護されます。この場合、映像を作った人、日本語に翻訳した人が著作者となります。
★編集者著作物
編集する人がどのような順序で載せるかなど創造性を発揮している創作物である百科事典、新聞、雑誌。
コンピュータによって検索できるようにしたデータベースも著作物として保護されます。
4.著作者の権利
「著作者の権利」には大きく2つあります。<1>著作者人格権と、<2>著作権(財産権)と呼ばれているものです。
<1>著作者人格権
著作者者人格権とは、著作者が精神的、感情的に傷つけられないようにする権利で、さらに細かく3つの権利に分かれます。
○公表権
未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利
○氏名表示権
著作者の名前(実名やペンネーム)を公表するかしないかを決める権利
○同一性保持権
著作物の内容や題名を著作者の了解なしに勝手に改変されない権利
<2>著作権(財産権)
著作権(財産権)とは、著作者が経済的(金銭的)に損失を被ることを保護するものです。
○複製権
自分の著作物を無断で複製されない権利
○上演・演奏権
自分の著作物を無断で公衆に上演、演奏されない権利
○上映権
自分の著作物を無断で公衆に上映されない権利
○公衆送信権
自分の著作物を無断で公衆に送信(テレビやインターネットで公表)、あるいは公衆送信された著作物を公に伝達されない権利
○口述権
論文や小説など言語の著作物を無断で公衆にに口頭で伝達されない権利
○展示権
美術・写真の著作物を無断で公衆にに展示されない権利
○譲渡権
著作者に無断で公衆に譲渡されない権利
○貸与権
著作物を無断で公衆に貸与(レンタル)されない権利
○頒布権(はんぷけん)
著作物を無断で公衆に頒布(譲渡・貸与、広い意味)されない権利
○二次的著作物の創作権(翻訳・翻案)
著作物の原作を翻訳、映画化等することによって、無断に加工されない権利
○二次的著作物の利用権
無断で二次的著作物を利用されない権利
5.著作権の保護期間
著作権の保護期間は、著作者の死後50年、無名または変名で公表された著作物の保護期間は、著作物公表後50年が通常です。
「著作者の死後」、「公表後」というのは、著作権者が亡くなった年または著作物が公表された年の翌年の、1月1日からと決められています。
ただし、映画の著作物の保護期間は、映画が公表されてから70年間で、著作者は法律の定めによって映画製作者(映画会社)に帰属します。
6.当事務所をご利用いただくお客様のメリット
<1>時間と労力の節約
一般の方に著作権法はなじみのない法律です。著作権の登録をするために著作権法の勉強からはじめ、著作権登録の種類や文化庁への登録手続きを調べていたのでは、たくさんの労力と時間がかかります。
当事務所をご利用いただければ、お客様はオフィスやご自宅にしながらにして文化庁への著作権の登録ができます。
<2>保護・活用に関する様々なご提案
たとえば、著作権の譲受のために著作権の登録をする場合を例にあげます。
著作権の譲渡をする場合は当然ながら、相手方と譲渡契約書を結ぶことになりますが、その場合、著作法27条(翻訳権・翻案権等)、28条(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)は契約書等で縛りつけるのが常識です。
当事務所はお客様の立場に立って様々なご提案をいたします。
著作権登録に伴う、契約書等の作成も行っております。
・著作権譲渡契約書
・著作権創作委託契約書
・出版権設定契約書
・ソフトウェア又はプログラム開発委託契約書 など
<3>ご相談が無料
当事務所へご依頼いただいたお客様は著作権に関するご相談が無料になります。例えば、著作権が侵害された、著作権の契約書を作りたい、著作権をもっと活用したい、著作権を担保にお金を借りたいなど、様々な相談が無料になります。
当事務所は日本行政書士会連合会の所定の研修を終了した著作権の相談員行政書士ですので、お客様は安心してご依頼することができます。著作権のご相談は、当事務所へお気軽にご相談ください。
対応地域
宮城県全域:仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,富谷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町
お客様が仙台までお越しいただかなくても宮城県内であれば出張も可能ですので、仙台市外のお客様も安心してご相談ください。